認知症と診断されたご家族を抱え、先の見えない不安や戸惑いを感じていらっしゃるかもしれません。日々の変化に心を痛め、どのように接したら良いのか悩むこともあるでしょう。
そんな中でも、「何かできることはないか」と思う気持ちが、今このブログを開いてくださっているのだと思います。
このブログでは、認知症のメカニズムを脳科学と神経心理学の視点から解説し、ご家族がより深く理解するための一助となることを目指します。そして、認知症の方との関わり方、支えとなる情報、そして共に歩むためのヒントを、同じように認知症と関わる全ての方々に向けてお伝えしたいと思います。
「認知症の人」という表現と、認知症の「人」という捉え方は、全く異なる考え方です。私たちは、認知症を持つ方を一人の「人」として関わることを決して忘れてはなりません。その方々も私たちと同じように、人間の尊厳や羞恥心といった感情を持っています。だからこそ、「人」として関わらなければならない。
認知症とは:脳の機能障害によって引き起こされる複合的な状態
認知症は、特定の病名ではなく、様々な原因によって脳の神経細胞が徐々に失われたり、機能が低下したりすることで、記憶、思考、判断力、言語など、認知機能が持続的に低下していく状態を指します。単なる加齢による物忘れとは異なり、日常生活に支障をきたすほど進行していくのが特徴です。
脳科学から見た認知症のメカニズム
私たちの脳は、約1000億個もの神経細胞(ニューロン)が複雑なネットワークを形成し、電気信号や化学物質を介して情報を伝達し合っています。この精緻なネットワークによって、私たちは記憶したり、考えたり、感情を抱いたり、行動したりすることができます。
認知症の多くの場合、この神経細胞やそのネットワークに異常が生じます。代表的な疾患であるアルツハイマー病では、「アミロイドβ」と呼ばれるタンパク質が脳内に蓄積し、神経細胞の機能を阻害したり、死滅させたりすることがわかっています。また、「タウタンパク質」の異常な蓄積も神経細胞の骨格を壊し、情報伝達を阻害すると考えられています。
脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などによって脳の血流が途絶え、神経細胞が酸素や栄養を受け取れなくなることで起こります。これにより、脳の一部の機能が失われ、認知機能の低下を引き起こします。
レビー小体型認知症では、「αシヌクレイン」というタンパク質が脳内に異常に蓄積し、「レビー小体」と呼ばれる構造物を形成します。これが、幻視、パーキンソン症状(手足の震え、動作の緩慢さなど)、認知機能の変動といった特徴的な症状を引き起こします。
前頭側頭型認知症は、脳の前頭葉や側頭葉の神経細胞が選択的に変性・萎縮していくことで発症します。これにより、人格の変化、行動の異常、言語理解や表出の困難さなどが現れます。
神経心理学から見た認知症の症状
神経心理学は、脳の機能と心の働き(認知機能、感情、行動など)の関係性を研究する学問です。認知症においては、脳のどの領域が影響を受けているかによって、現れる認知機能の障害が異なります。
- 記憶障害: 海馬と呼ばれる脳の領域は、新しい情報を記憶する上で重要な役割を果たします。アルツハイマー病などで海馬が障害されると、最近の出来事を覚えられなくなる(近時記憶の障害)といった症状が現れます。
- 実行機能障害: 前頭前野は、計画を立てる、目標を設定する、行動を順序立てて実行する、問題解決をするなど、高度な認知機能を司ります。この領域が障害されると、段取りがうまくできなくなったり、複数のことを同時にこなせなくなったりします。
- 注意障害: 脳の様々な領域が連携して、必要な情報に注意を向け、不要な情報を無視する働きを担っています。認知症が進行すると、注意を持続させることが難しくなったり、複数の刺激の中から必要なものを選び取ることが困難になったりします。
- 言語障害: 言葉を理解したり、話したりする能力は、側頭葉や頭頂葉など、脳の広範囲のネットワークによって支えられています。認知症の種類や進行度合いによって、言葉が出てこなくなる(失語)、人の言うことを理解できなくなる、同じことを何度も繰り返すなどの症状が現れます。
- 視空間認知障害: 目で見た情報を処理し、空間における位置関係や方向、奥行きなどを認識する能力が低下することがあります。これにより、道に迷いやすくなったり、物の配置がわからなくなったりします。
これらの認知機能の低下に伴い、感情のコントロールが難しくなったり、意欲が低下したり、不安や抑うつなどの精神症状が現れることもあります。また、幻覚や妄想、睡眠障害、食行動の変化など、行動面の変化が見られることもあります。
認知症を抱える家族への対応:理解と受容、そして共に歩む姿勢
認知症の方への対応で最も大切なことは、病気を理解し、その人のペースに合わせて寄り添うことです。認知症によって生じる様々な症状は、その人自身の意思によるものではなく、脳の機能障害によるものであるという視点を持つことが重要です。

コミュニケーションの工夫
- ゆっくりと、はっきりとした口調で話す: 早口や複雑な言い回しは避け、短い言葉で具体的に伝えましょう。
- アイコンタクトを大切にする: 目を見て話すことで、安心感を与え、注意を引きつけやすくなります。
- ジェスチャーや視覚的な手がかりを活用する: 言葉だけでなく、身振り手振りや写真、絵などを使うことで、理解を助けることができます。
- 質問は一つずつ: 複数の質問を同時にすると混乱を招く可能性があります。
- 間違いを指摘するよりも、受け止める: 事実と異なることを言っても、頭ごなしに否定するのではなく、「そう思われたんですね」と受け止め、安心できる言葉をかけましょう。
- 過去の話題は共有しやすい: 昔の思い出話は、比較的鮮明に覚えていることが多いので、積極的に話しかけてみましょう。
- 非言語的なコミュニケーションも大切に: 表情や声のトーン、触れ合いなども、気持ちを伝える大切な手段です。
日常生活のサポート
- できることはご自身でしてもらう: 過保護にせず、できる範囲で役割を持ってもらうことが、意欲の維持につながります。
- 生活リズムを整える: 規則正しい食事、睡眠、運動は、心身の安定に繋がります。
- 安全な環境を整える: 転倒防止のための工夫、火や水の取り扱いへの注意など、安全に過ごせる環境を整えましょう。
- 環境の変化は最小限に: 急な環境の変化は混乱を招きやすいため、できるだけ安定した環境を保ちましょう。
- スケジュールを見える化する: カレンダーやメモなどを活用し、予定を把握しやすくすることで、不安を軽減できます。
感情への配慮
- 感情を否定しない: 怒りや悲しみなど、どのような感情も受け止め、「つらいですね」「寂しいですね」と共感する姿勢が大切です。
- 安心できる言葉をかける: 「大丈夫ですよ」「ここにいますよ」といった言葉は、安心感を与えます。
- 好きなこと、楽しめる時間を作る: 音楽を聴く、散歩をする、趣味の活動をするなど、その人が心地よく過ごせる時間を作りましょう。
- 焦らず、穏やかな気持ちで接する: 介護する側の気持ちの余裕が、良い関係を築く上で不可欠です。
認知症と関わる全ての人へ:共に支え合う社会を目指して
認知症は、ご本人だけでなく、ご家族、そして周りの人々にとっても大きな課題です。認知症の方々が地域の中で安心して暮らしていくためには、社会全体の理解と支え合いが不可欠です。ただそんな中でも、もどかしさやイライラは募りフラストレーションは高くなりがちです。そんな時の対処法はこちら。
- 認知症サポーター: 認知症について正しく理解し、地域や職場でできる範囲で認知症の方やその家族を支援する「認知症サポーター」の輪を広げることが重要です。
- 地域の資源を活用する: 地域包括支援センターや認知症カフェなど、認知症の方やその家族を支援する様々な資源があります。積極的に情報を収集し、活用しましょう。
- 専門家との連携: 医師、ケアマネージャー、ヘルパー、作業療法士、言語聴覚士など、様々な専門家と連携し、チームでサポートしていくことが大切です。
- 情報交換の場を持つ: 同じような経験を持つ家族会に参加することで、悩みを共有したり、情報交換をしたりすることができます。
- 偏見や誤解をなくす: 認知症は誰にでも起こりうる病気であり、特別なことではありません。正しい知識を持ち、偏見や誤解のない社会を目指しましょう。

認知症の方との時間は、時に困難を伴うかもしれませんが、その中で見せる笑顔や穏やかな表情は、私たちにとってかけがえのない宝物です。脳科学や神経心理学の知識を深め、対応のヒントを実践することで、より穏やかで温かい関係を築けるはずです。

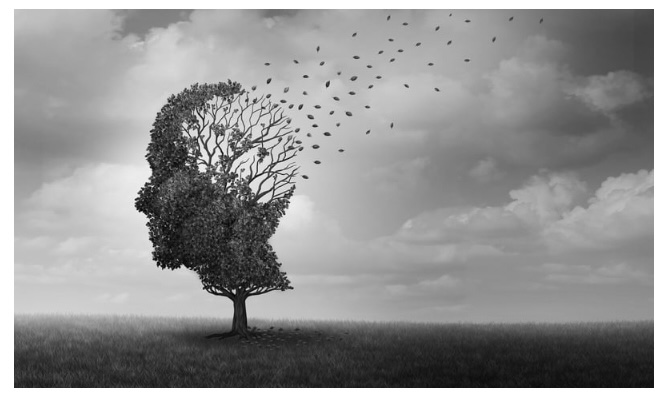


コメント